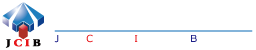「人手不足で困っています」
経営者の集まりでも、ニュースでも、この言葉を聞かない日はありません。飲食店、介護施設、物流業界、小売店…あらゆる業界で人手不足が叫ばれています。帝国データバンクの調査によれば、正社員が不足している企業は全体の50%を超え、特に飲食業や建設業では70%以上が人手不足を感じているとされています。
しかし、20年間経営の現場に立ち続けてきた私は、この「人手不足」という言葉の裏に隠された本質的な問題に気づき始めました。それは、純粋に「人が足りない」のではなく、「安く都合よく働いてくれる人が不足している」という、資本主義社会の構造的な矛盾です。
この問題を直視せずに、表面的な対症療法だけを続けていては、日本経済の未来は暗いままです。今こそ、経営者も従業員も消費者も、この問題の本質と向き合う時が来ています。
本当に「人」が足りないのか?

数字が示す矛盾
総務省の統計によれば、日本の生産年齢人口(15〜64歳)は確かに減少傾向にあります。1995年の8,726万人をピークに減少を続け、2023年には7,395万人まで減少しました。この数字だけを見れば、確かに「人手不足」は避けられない現実のように思えます。
しかし、ここで考えてみてください。求人倍率が高い業界と低い業界が明確に分かれていることを。IT業界の一部職種や専門性の高い職種では、高待遇の求人が出ればすぐに応募があります。年収800万円以上のITエンジニアの求人には、数日で数十件の応募が集まることも珍しくありません。
一方で、飲食業や介護業界では「どれだけ募集しても人が来ない」と嘆く声が絶えません。時給1,000円で週6日勤務、シフト制で休日も不定期という条件では、応募がゼロという事態も発生しています。この差は何を意味しているのでしょうか。
「人がいない」のではなく「条件が合わない」
私自身、採用活動を通じて痛感したことがあります。創業当初、私も「人手不足」に悩まされていました。求人広告を出しても応募はゼロ。ハローワークに通っても結果は同じ。「これが人手不足の現実か」と諦めかけていました。
しかし、ある時、思い切って条件を見直しました。給与を業界平均より2割上げ、勤務時間を明確化し、完全週休2日制を導入し、福利厚生を充実させたのです。すると驚くべきことが起きました。わずか1週間で10件以上の応募があり、その中には経験豊富な優秀な人材も含まれていたのです。
それまで「人手不足で」と言っていた自分が恥ずかしくなりました。人は確かに存在していました。ただ、提示された条件では働きたくないだけだったのです。これを「人手不足」と呼ぶのは、正確ではありません。正しくは「適正な労働条件を提示できる企業の不足」「魅力的な職場の不足」と言うべきでしょう。
求人市場の二極化
現在の求人市場は、明確に二極化しています。高待遇の企業には人材が集まり、低待遇の企業には誰も応募しない。この単純な事実を、多くの経営者が認めたがりません。
私が参加する経営者の勉強会でも、よくこんな声を聞きます。「うちは給与も悪くないのに人が来ない」。しかし、よく話を聞いてみると、その「悪くない」給与は業界平均レベル。勤務時間は長く、休日も不定期。これでは「悪くない」どころか、むしろ「避けられる条件」なのです。
「安く都合よく」という幻想

昭和の成功体験からの脱却
多くの経営者が抱えている問題は、過去の成功体験から抜け出せないことです。「昔はもっと安い給与でも人が集まった」「残業も文句を言わずにやってくれた」「新入社員は3年は辞めずに働くものだった」そんな時代と今を同列に語ることが、そもそもの間違いなのです。
私の会社の先輩経営者たち(60代以上)と話をすると、よくこんな話を聞かされます。「俺たちの時代は、給料が安くても一生懸命働いた」「夜中まで残業しても文句一つ言わなかった」「それが当たり前だった」。
しかし、その「当たり前」が通用した時代背景を忘れてはいけません。終身雇用が機能し、年功序列で給与が上がり、退職金も十分に保証され、将来への安心があった時代です。今はその前提がすべて崩れています。非正規雇用が増え、給与は上がらず、退職金も期待できない。そんな時代に、昭和の価値観を押し付けることが、いかに無理なことか。
バブル崩壊後の「失われた30年」がもたらしたもの
バブル崩壊後の「失われた30年」の中で、企業は人件費削減を最優先課題としてきました。非正規雇用を増やし、給与を抑え、「効率化」という名の下に労働者への負担を増やし続けました。派遣労働者が増え、契約社員が増え、正社員でも給与は据え置かれ、ボーナスはカットされました。
私が社会人になった2000年代初頭、先輩社員から聞いた言葉が今でも忘れられません。「バブルの頃は、新入社員でもボーナスが100万円超えたんだぞ」。当時の私は、「そんな時代があったのか」と驚きました。しかし今思えば、それが異常だったのではなく、今が異常なのかもしれません。
その結果として生まれたのが、今の「人手不足」という皮肉な現象です。30年間、労働者を「コスト」として削り続けた結果、誰も働きたがらない労働市場が出来上がってしまったのです。
都合の良い働き方の終焉
「必要な時だけ来てほしい」「繁忙期だけ働いてほしい」「急な欠勤には対応してほしくないが、急なシフト変更には応じてほしい」「経験豊富なベテランが欲しいが、給与は新人レベルで」こうした企業側の都合だけを優先した雇用条件が、もはや通用しなくなっているのです。
ある飲食チェーンの経営者が、こんな愚痴をこぼしていました。「うちは時給1,050円も出してるのに、誰も応募してこない。みんな贅沢になったものだ」。しかし、その求人内容をよく見ると、週5日勤務必須、土日祝日は必ず出勤、シフトは前日変更あり、交通費なし、昇給なし。これで「贅沢」と言われても、誰が応募するでしょうか。
働く側も賢くなりました。自分の時間、健康、将来を犠牲にしてまで、都合よく働くことの無意味さに気づいています。SNSを通じて情報は瞬時に共有され、「ブラック企業」のレッテルは一瞬で広がります。就職口コミサイトには、実際の労働環境が赤裸々に書かれ、求職者は事前に企業の実態を知ることができます。
20年前なら通用した「とりあえず安い給与で募集して、文句を言わない人を探す」という手法は、完全に時代遅れになっているのです。情報の非対称性が解消された今、企業は本当の意味で「選ばれる側」になったのです。
構造的問題としての人手不足
価格転嫁できない経済構造
日本経済が抱える根本的な問題は、適正な価格転嫁ができないことです。人件費を上げたくても、商品やサービスの価格を上げられない。価格を上げれば顧客が離れる。この悪循環が、「安く働いてくれる人」を求め続ける構造を生んでいます。
私の会社でも同じ経験をしました。サービスの質を上げるために人件費を増やしたい。優秀な人材を採用し、適正な給与を払いたい。しかし、その分を価格に転嫁しようとすると、既存顧客から「高い」というクレームが来る。競合他社は相変わらず低価格で勝負してくる。
ある時、思い切って価格を15%値上げしました。覚悟していた通り、一部の顧客は離れていきました。売上は一時的に30%も落ち込みました。しかし、半年後、状況は一変しました。適正価格を払ってくれる「良い顧客」だけが残り、従業員の給与を上げたことで離職率が激減し、サービス品質が向上し、結果として新規顧客が増え、売上は値上げ前を超えたのです。
この経験から学んだことは、「安い価格で勝負する」という戦略そのものが、持続可能でないということです。
デフレマインドの弊害
30年近く続いたデフレ経済の中で、「安くて当たり前」という消費者マインドが定着してしまいました。品質の高いサービスには相応の対価が必要だという認識が薄れ、「できるだけ安く」が最優先される社会になったのです。
牛丼一杯300円、ハンバーガー100円、カットサロン1,000円。確かに消費者にとっては嬉しい価格です。しかし、その裏で働く人々の給与はどうなっているでしょうか。最低賃金ギリギリ、社会保険なし、昇給なし。そんな条件で働かされている人々が、この「安さ」を支えているのです。
しかし、安さを追求すればするほど、そこで働く人々の給与は下がります。給与が下がれば消費が冷え込み、さらに安さが求められる。この負のスパイラルこそが、「安く都合よく働いてくれる人の不足」を生んでいる根本原因です。
私たち消費者も、この構造の共犯者なのです。「安ければいい」という価値観を改めない限り、この問題は解決しません。
中小企業の限界
大企業であれば、ある程度の給与水準を保つことができます。ブランド力があり、価格決定力があり、福利厚生も充実しています。しかし、日本企業の99.7%を占める中小企業は、価格競争の最前線に立たされています。
私自身、中小企業の経営者として、この矛盾と日々向き合っています。従業員に適正な給与を払いたい。大手企業並みの福利厚生を用意したい。働きやすい環境を整えたい。しかし、大手企業との価格競争に負けないためには、コストを削減せざるを得ない。
ある取引先から、こんなことを言われたことがあります。「御社のサービスは良いんだけど、A社より20%高いんだよね。A社と同じ価格にしてくれたら発注するけど」。A社の従業員の給与や労働環境を知っている私は、その価格では絶対に受けられないと断りました。しかし、そういった選択ができる中小企業は、実は少数派なのです。
この板挟みの中で、多くの中小企業が「人手不足」に苦しんでいるのです。適正な給与を払えば赤字になり、給与を抑えれば人が来ない。この二律背反の中で、廃業を選ぶ企業も少なくありません。
経営者が直面すべき現実
投資としての人件費
20年の経営経験の中で、私が最も後悔しているのは、人件費を「コスト」として見ていた時期があることです。削減すべき費用、抑えるべき支出。そう考えていた時期の会社は、確かに短期的には利益が出ましたが、長期的には成長が止まりました。
創業5年目、業績が伸び悩んでいた時期のことです。私は人件費を削減することで利益を確保しようとしました。昇給を凍結し、ボーナスをカットし、新規採用を控えました。その年の決算書は、確かに黒字でした。しかし、翌年から優秀な社員が次々と退職していきました。残った社員のモチベーションは下がり、サービス品質は低下し、顧客満足度は急落しました。
その経験から学んだことは、人件費は「投資」だということです。優秀な人材に適正な報酬を払うことで、生産性は上がり、顧客満足度は向上し、結果として売上も利益も増えます。この当たり前の事実に、なぜ多くの経営者が気づかないのでしょうか。
投資には回収期間があります。設備投資なら5年、10年のスパンで考えます。しかし、人材投資も同じです。今日払った給与が、明日すぐに売上になるわけではありません。しかし、1年後、3年後には、その投資は必ず返ってきます。その長期的視点を持てるかどうかが、経営者の資質を分けるのです。
選ばれる企業になる
「人手不足」と嘆く前に、経営者が自問すべきことがあります。「自分の会社は、人が働きたいと思える会社だろうか?」「家族や友人に自信を持って勧められる職場だろうか?」「自分が従業員だったら、この会社で働き続けたいと思うだろうか?」
私は3年前、大規模な待遇改善を実施しました。給与水準を業界平均の1.5倍に引き上げ、完全週休3日制を導入し、リモートワークを全面的に推進しました。社内副業を認め、スキルアップのための研修費用は全額会社負担としました。経営陣からは「そんなことをしたら会社が潰れる」と猛反対されました。
しかし、結果は正反対でした。応募者は急増し、それまで月に2〜3件だった応募が、月に50件以上になりました。面接に来る人材の質も劇的に向上しました。そして何より、離職率が激減したのです。それまで年間30%だった離職率が、わずか5%にまで下がりました。
従業員のモチベーションが上がったことで、生産性は1.8倍になりました。顧客満足度は向上し、リピート率が上がり、口コミで新規顧客が増えました。売上は前年比150%で推移し、利益率も改善しました。人件費は確かに増えましたが、それ以上に売上が伸びたため、営業利益率は逆に向上したのです。
「人手不足」という言葉は、社内から完全に消えました。むしろ、優秀な人材を断らなければならないという、贅沢な悩みを抱えるようになりました。
覚悟を決める時
経営者には覚悟が必要です。「安く都合よく働いてくれる人」を探し続けるのか、それとも「適正な対価を払って、共に成長する仲間」を求めるのか。この選択が、今後の企業の命運を分けます。
前者を選べば、一時的にはコストを抑えられるかもしれません。短期的には利益が出るかもしれません。しかし、長期的には人材の質の低下、離職率の上昇、企業イメージの悪化を招きます。結果として、どんどん競争力を失い、いずれは市場から淘汰されていくでしょう。
後者を選べば、短期的にはコストが上がります。最初の1年は赤字になるかもしれません。しかし、長期的には強固な組織が作られ、持続可能な成長が実現します。優秀な人材が集まり、イノベーションが生まれ、競争優位性が確立されます。
私は後者を選びました。そして、その選択は正しかったと確信しています。
これからの人材戦略
発想の転換が必要
「人手不足」という問題を解決するためには、根本的な発想の転換が必要です。「どうすれば安く人を雇えるか」ではなく、「どうすれば人が働きたいと思える会社を作れるか」、
この問いに真剣に向き合う時が来ています。
具体的には、以下のような施策が考えられます。
給与体系の見直し:業界平均ではなく、生活に必要な金額を基準に設定する。東京で一人暮らしをするなら、最低でも手取り25万円は必要です。成果に応じた明確な評価制度を導入し、頑張った人が報われる仕組みを作る。年功序列ではなく、実力主義で評価する。
働き方の柔軟化:リモートワーク、フレックスタイム、週休3日制など、多様な働き方を認める。育児や介護と両立できる環境を整える。副業を認め、個人の成長を支援する。「会社に縛られる」のではなく、「会社を活用する」という発想に転換する。
キャリアパスの明確化:どのようなスキルを身につければ、どう成長できるかを明示する。3年後、5年後、10年後のキャリアビジョンを一緒に描く。社内昇進のルートだけでなく、独立や転職も視野に入れた育成計画を立てる。
企業文化の改善:心理的安全性が高く、失敗を恐れずチャレンジできる環境を作る。上司と部下の関係ではなく、フラットなチーム文化を醸成する。「報告・連絡・相談」ではなく、「対話・共創・実験」を重視する。
透明性の向上:経営状況を社員に開示し、共に考える文化を作る。給与体系や評価基準を明確にし、ブラックボックスをなくす。社員の声を経営に反映させる仕組みを作る。
社会全体での意識改革
経営者だけの問題ではありません。消費者も、投資家も、政策立案者も、この構造的問題に向き合う必要があります。
適正な価格で適正なサービスを受ける。企業は適正な利益を上げ、従業員に適正な給与を払う。この当たり前のサイクルを取り戻さない限り、「人手不足」という名の構造的問題は解決しません。
消費者は、「安ければいい」という価値観を見直す必要があります。100円のハンバーガーの裏で、誰かが最低賃金で苦しんでいることを想像してください。300円の牛丼の裏で、誰かが長時間労働を強いられていることを知ってください。
投資家は、短期的な利益だけでなく、長期的な持続可能性を評価する必要があります。人材への投資を「コスト」として削減を求めるのではなく、「成長のための投資」として評価してください。
政策立案者は、最低賃金の引き上げだけでなく、適正価格での取引を促進する仕組みを作る必要があります。下請け企業への不当な値下げ要求を規制し、公正な取引を実現してください。
私たちは、安さだけを追求する社会から、質と持続可能性を重視する社会へと変わる必要があるのです。それは簡単なことではありません。しかし、それをしなければ、日本経済の未来はありません。
未来への投資
20年間経営を続けてきて、確信していることがあります。人材への投資こそが、最も確実なリターンを生む投資だということです。
設備投資は陳腐化します。技術投資は時代遅れになります。しかし、人材への投資は決して無駄になりません。たとえその社員が会社を辞めたとしても、その投資は業界全体の底上げにつながり、巡り巡って自社にも返ってきます。
「人手不足」と嘆く時間があるなら、自社の労働条件を見直してください。給与は適正ですか? 働く環境は快適ですか? 従業員の声に耳を傾けていますか? 成長の機会を提供していますか? 心理的安全性は確保されていますか? 透明性のある経営をしていますか?
これらの問いに自信を持って「YES」と答えられる企業には、必ず人が集まります。「人手不足」は、企業が変わるための警鐘なのです。その警鐘を無視し続けるのか、それとも真摯に受け止めて変革するのか。その選択が、企業の未来を決めるのです。
まとめ
昨今叫ばれている「人手不足」の本質は、労働市場における需要と供給のミスマッチではありません。それは、長年にわたって積み重ねられてきた「労働を安く買い叩く」という企業文化と、それを許容してきた社会構造の歪みが表面化したものです。
経営者として20年を過ごす中で、私は多くの過ちを犯してきました。人件費を削減し、従業員に過度な負担を強い、短期的な利益を優先した時期もありました。しかし、その失敗から学んだことは明確です。人は、尊重され、正当に評価され、成長の機会が与えられる場所でこそ、最大のパフォーマンスを発揮するということです。
「安く都合よく働いてくれる人」を探し続ける時代は終わりました。これからは「共に成長し、共に価値を創造するパートナー」を求める時代です。この転換ができた企業だけが、真の意味で「人手不足」を克服し、持続可能な成長を実現できるのだと、私は確信しています。
変化は痛みを伴います。しかし、変化しなければ、もっと大きな痛みが待っています。今こそ、経営者も従業員も消費者も、みんなで一緒にこの問題に向き合い、より良い社会を作っていく時なのです。
※参考資料